市進ホールディングス 50年史 「2001~2005年」
教育の多様化
~教育サービスの高度化~
「ゆとり教育」がもたらしたもの

個太郎塾の授業の様子
1998年に個別指導塾分野へ参入し千葉で展開していた個太郎塾は2001年に東京都に進出し、翌年には神奈川県でも教室を開いた。
個太郎塾の講師1人に生徒2人という1対2の指導方法は、他社の多くが採用する1対3ないし4に比べて評価が高く、ビジネスモデルとして十分な成功を収めていた。各家庭に対しては、1対1よりリーズナブルであり、1対3ではひとりの生徒に対応する時間が短く、1対2が指導方法としては最適、というシンプルな訴求が的を射ていた。指導側としても、1対2であればひとりが演習をしている間、もうひとりに説明をするというように効率的な指導が行える。チェーン展開を考える上でも1対2の指導体制は理にかなうものだった。
時代による教育の変化は本来ゆるやかに進むものだが、2002年4月に始まった新学習指導要領、いわゆる「ゆとり教育」は教育現場に急変をもたらした。その余波は社会全体にも広がり、メディアは連日のようにゆとり教育について取り上げた。“円周率は3”に象徴されるその教育内容は、各家庭にも漠然とした不安を抱かせるに十分なものだった。
小学生の子を持つ家庭での不安感は、「我が子をこのまま公立中学校へ通わせていいのだろうか」という思いに変わり、中学受験に向けて塾へ通わせることが社会風潮のようになっていった。市進もこの時期に、限定的にではあるが入会者数を伸ばしている。
2003年には、小学校5、6年生向けの幅広い進学ニーズに応える「学力強化コース」が新設された。これまで小学部は中学受験をターゲットとしてきたが、公立中学へ進学する小学生に向けたコースとしてつくられた。ゆとり教育によって、学校で習う内容が薄くなることで、そのまま中学校の学習内容にすんなり接続できるのかという、これもゆとり教育に対する不安から生み出されたものである。
教育の質を問う、「首都圏学力測定」の実施
2003年6月には田代英壽が代表取締役社長となる。自らの考える教育への思いを実現させていくため2004年3月に「首都圏学力測定」を実施した。
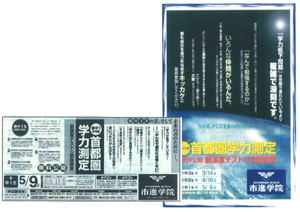
ポスターやチラシで大々的に募集
首都圏学力測定は、学習塾の立場から学力低下の現状を探る初の試みとして、中学1年生~3年生に対してテストとアンケートを毎年行うものである。これにより、生活習慣や本人の自己肯定感などと学力の相関関係を測るという狙いがあった。実際、測定結果からはアンケート内容と学力に相関関係が見出せるデータが出た。例えば、読書量の多い生徒の学力が高かったり、1日にテレビを4時間以上観る生徒とそうでない生徒にも、明らかな学力の差が見られるなど、その結果はメディアでもしばしば取り上げられていた。
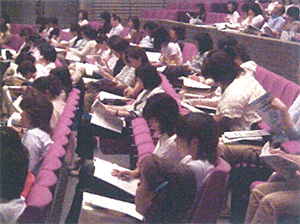
当日は大勢の保護者が集まった
現在では、文部科学省が「全国学力・学習状況調査」を実施しているが、政府が取り組む何年も前からすでに行っていたことになる。次代の教育を考え、社会で活躍する人材を育てていくためには、より良い教育が必要であり、そのための勉強の必要性を多角的に捉えるために学習塾として行った、いわば社会貢献活動の一環ともいえる。
2004年12月には、日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場した。
2005年には、それまで個学舎が運営していた個太郎塾を市進学院内で展開することとなった。すでにこの頃には、塾へ通う生徒のおよそ4割が個別指導塾を選択するという社会情勢となっており、かつては補習的な意味合いの強かった個別指導塾がマーケットを獲得したといえる。
社会が成熟していくなかで、教育にも多様性が求められていた。各家庭では子供の個性を尊重しようとし、その思いは塾への要請となり、集団指導だけでなく個別指導を選択する傾向が強まったのである。
